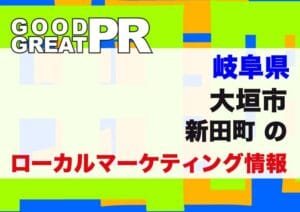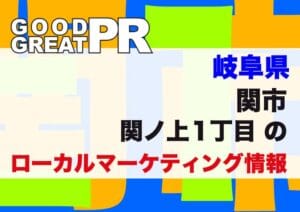AIDMAの法則は、ポスティングで活用したいマーケティングの専門用語です。チラシを手にとった人々が、商品を購入する消費者になるまでの心理に注目します。上手く活用することで広告コストを抑え、効果的なポスティングを実施することができます。
今回は、ポスティングの評判を高めるAIDMAの法則について理解を深め、効果的なポスティングの仕方について解説します。
AIDMAの法則を使ったポスティングの評判の高め方
チラシやビラを作って配る前に、AIDMAの法則を効果的に使用し、計画を立ててポスティングをすれば高い反響率を期待できます。
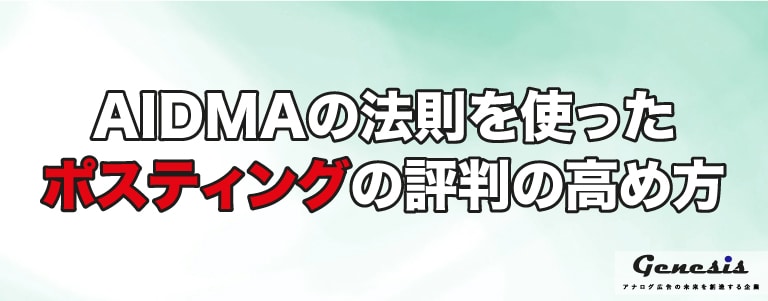
ポスティングの評判を高めるには、さまざまなポイントを押さえることで実現可能です。
主な3つのポイントを詳しく紹介していきます。
・ポスティングするチラシやビラの内容を工夫する
・継続的にポスティングする
目的によって配るターゲット・エリアを具体的に決める
チラシを配ることは「AIDMAの法則」でいうと「Attention(注意)」で、消費者が商品に気づくきっかけになりますが、闇雲にポスティングしても効果はありません。
例えば、単身用のマンションが立ち並ぶエリアに、子ども向けの学習塾のチラシを入れても高い反響率が得られないでしょう。
このため、どのような消費者に商品を購入して欲しいのか、目的を具体的に決めることで、ポスティングをするエリアが決まってきます。
例えば、単身用マンションのエリアには、「少ない荷物ならリーズナブルに引っ越しができる」など一人暮らしの方が喜ぶサービスや商品を売り込むチラシを配ると有効でしょう。
反対に、誰もが利用できるようなスーパーやホームセンターなどは、近隣のエリアにポスティングすると来店する人が増加します。
また、夏休みや冬休みなど長期休み前の季節に、旅行のチラシを配布するなど、季節によってポスティングすると効果が出るものもあります。
さらに、性別・年収・町丁など様々な具体的条件で細かく検索できるGISデータを活用することで、宣伝の効果を上げられます。
ポスティングするチラシやビラの内容を工夫する
消費者の「Interest(興味)」と「Desire(欲求)」を動かすため、チラシのデザインや内容を工夫します。
まず、消費者にチラシやビラを見てもらうには、チラシやビラの形を他のものとは異なるようにすると、消費者の目にとまるでしょう。
例えば、ハガキにするとチラシと比べて光に反射しないため、視認性が高まると言われています。
また、冷蔵庫に貼り付けられるようなマグネット、ティッシュといったサンプルを入れてボリュームを出すと見てもらいやすくなります。
さらに、写真やキャッチコピーを使って消費者の「Interest(興味)」を引きつけるようにするのも良いでしょう。
人は、チラシなどの販促物を1〜2秒見ただけで、その商品がどのようなもので自分は興味があるかどうかを判断します。
例えば、リゾート写真や「シュノーケリングで海の生き物たちと触れ合うオプション付き」など書かれていると、このチラシは旅行会社が普段できないような海のアクティビティがついていることが分かります。
さらに、写真が消費者がイメージを想起しやすいものであることや、値段が意外と安いといったポイントがすぐに見てわかれば、消費者は興味を引きつけられるでしょう。
次に消費者の「Desire(欲求)」をかき立てるため、商品を使用したことがある口コミや体験談などが効果的です。
例えば、学童期の保護者に向けた通信教育の広告なら、「自分から学習するようになった」「学校のテストの点が上がった」など書かれていると、保護者は試してみたいという思いが出てくるかもしれません。
チラシの内容を読んでもらうためには、デザインを工夫し、写真やキャッチコピーを入れ、口コミや体験談を記載すると良いでしょう。
他にも、チラシのフォントや色を使いすぎないなど、ポスティングのデザインには工夫が必要です。
継続的にポスティングする
心理学者のヘルマン・エビングハウスが理論づけた「忘却曲線」によると、人は覚えたものを1ヶ月で79%忘れてしまいます。
このため、消費者に商品を「Memory(記憶)」してもらうには継続的にポスティングすることが必要です。
また、何度もポスティングすると、消費者は覚えるだけでなく商品に対して好印象をもつというロバート・ザイアンスが提唱した「単純接触効果(ザイアンス効果)」も期待できます。
できれば1ヶ月に1度以上ポスティングをすると、「Memory(記憶)」され、同時に消費者に好印象をもたれるでしょう。
ここまでくれば、消費者は商品を購入しようと決心します。
最後に、消費者が「Action(行動)」しやすいように、どのようにしたら商品を手に入れられるのか、分かりやすく記載してください。
例えば、お店の新規オープンであれば地図を載せる、QRコードでHPに簡単に飛ぶことができオンライン注文できるようにするなど、商品の入手の仕方を書いておくと親切でしょう。
ポスティングの評判を高めるAIDMAの法則まとめ
・目的によって配るターゲット・エリアを具体的に決めると、経費を抑えながら反響率を高められる「Attention(注意)」を向けてもらえます。
・写真やキャッチコピー、口コミを載せるなど、チラシやビラの内容を工夫することで興味をもってもらえる「Interest(関心)」や「Desire(欲求)」に訴えかけられます。
・継続的にポスティングすることで商品を覚えてもらい、購入へと促すよう「Memory(記憶)」され、購入のための「Action(行動)」ができます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
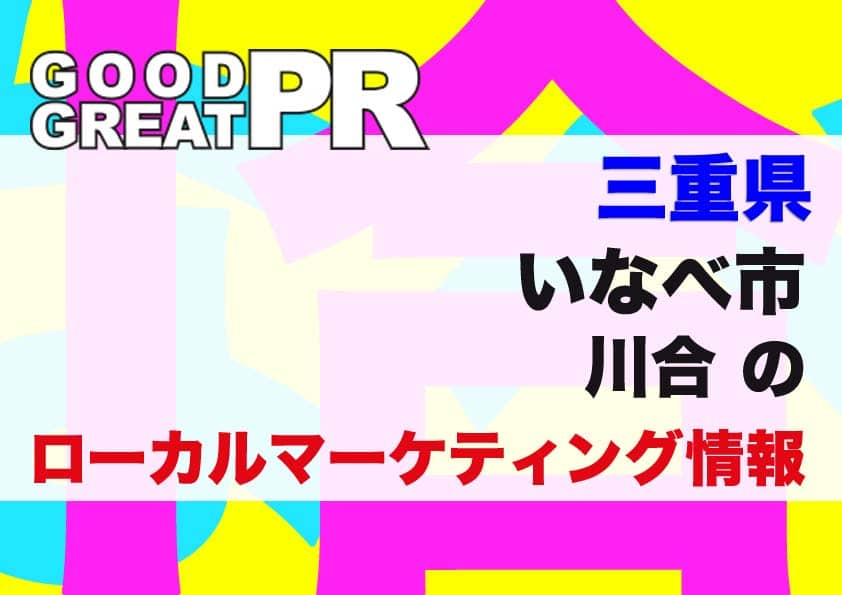 いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市川合のローカルマーケティング情報
いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市川合のローカルマーケティング情報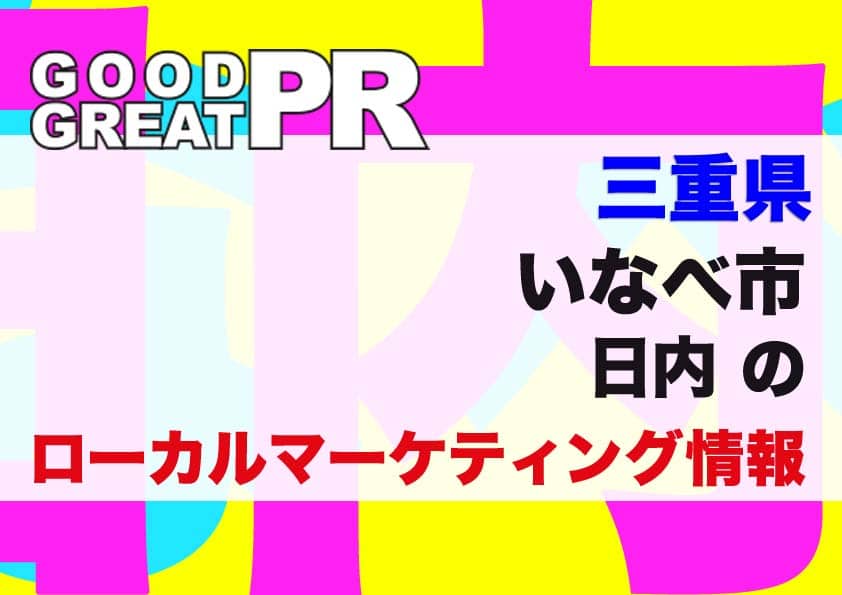 いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市日内のローカルマーケティング情報
いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市日内のローカルマーケティング情報 いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市上相場のローカルマーケティング情報
いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市上相場のローカルマーケティング情報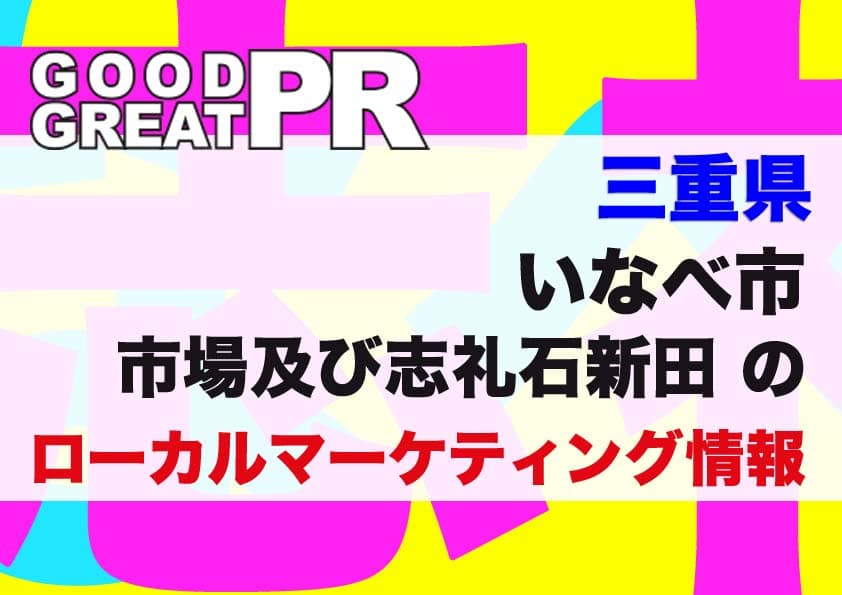 いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市市場及び志礼石新田のローカルマーケティング情報
いなべ市2024年3月8日【三重県】いなべ市市場及び志礼石新田のローカルマーケティング情報